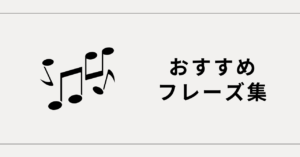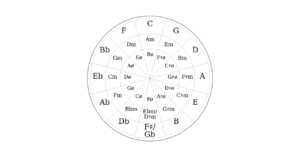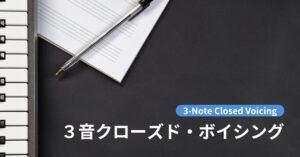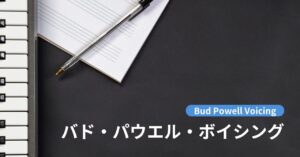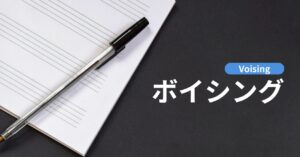スケールを覚えるメリットのひとつは、演奏を聴いているときに「今のフレーズはあのスケールね」と察する力がつくことだと思います。
単なる音の羅列にしか聴こえなかったものが、「◯◯スケール」というラベルをつけられるようになると、ぐっと整理されて、フレーズが覚えやすくなります。
今回は、スケールについての基本的な考え方を少し整理してみます。
スケールを覚えるのはしんどい
スケールの話題になると、多くの人が「このコードではこのスケールが使える」とか、「チャーチモードがどうこう」といった理論の話に触れると思います。
でも、ジャズピアノを始めて数年くらいの人がそれを知っても、正直ピンとこないと思います。初心者のうちから真面目にスケールを勉強しようとすると、理解も難しく、アドリブにも活かしづらいので挫折しがちです。
わたし自身も、最初からスケールを覚えようとしたわけではありません。ひたすら音源をコピーして、「あ、このフレーズってこのスケールで説明できるのか」と後から気づく、そんな順序でした。
とはいえ、スケールをまったく知らないのも考えものです。最低限の考え方だけでも知っておくと、耳コピや分析がずいぶん楽になります。
今回は、その「スケールの考え方」を中心に整理してみたいと思います。
スケールは「コードに対して使える音」の集まり
マーク・レヴィンの『THE JAZZ THEORY』という有名な理論書に、スケールについてこんな記述があります。
スケールとコードは同じものを2つの異なった形で表したものにすぎないのです。
Mark Levine (著), 愛川 篤人 (訳) 『ザ・ジャズ・セオリー』ATN,2004,p.30
「スケールとコードは、実は同じものを別の角度から見ているだけ」という考え方を初めて知ったときは、本当に目から鱗でした。
「このコードではこのスケールが使える」と説明されると、まるでスケールとコードが別々の道具のように聞こえます。でも実際はそうじゃないんですよね。
上手いプレイヤーは、スケールを 「あるコードに対して使える音の集まり」 として見ています。つまり コードとスケールを別物ではなく“一体のもの”として捉えている わけです。
これは音楽大学などで体系的に学んでいる人にとっては当たり前の感覚かもしれません。でも独学でジャズを学んでいると、この視点にはなかなかたどり着けないんじゃないかなと思います。
難しそうに聞こえるかもしれませんが、「スケールとコードは表裏一体」 という考え方を知っておくだけで、学習のスピードが一気に変わります。
知っておくだけでも、きっと練習の助けになるはずです。
主要なスケールは4つで十分
『THE JAZZ THEORY』には、非常に救いのある(?)記述があります。
ジャズの初心者のほとんどは、あれだけたくさんのコードがあるのだから、スケールもそれだけたくさんあるに違いないと思い込んでいます。それは間違いです。ほとんどすべてのコード・シンボルを、わずか 4つのスケールで解釈することが可能なのです。
・メジャー・スケール
・メロディック・マイナー・スケール
・ディミニッシュ・スケール
・ ホールトーン・スケール
Mark Levine (著), 愛川 篤人 (訳) 『ザ・ジャズ・セオリー』ATN,2004,p.30
なんと、ジャズに登場するほとんどのコードを、たった4つの基本スケールで解釈できると言ってくれているのです。これも本当に目から鱗の考え方でした。
もちろん、他にもさまざまな名前のスケールがあります。でも、まずはこの4つを押さえておけば十分だと思います。
具体的な例はまた別の記事で紹介しますが、私自身、ジャズを学んでいく中でこの4つのスケールの重要性を強く実感しています。
さらに付け加えるなら、ジャズ特有のサウンドを生む ブルー・ノート・スケール も含めた計5種類。この5つさえ押さえておけば、大抵のことはなんとかなると思います。
まとめ
今回は「スケールそのもの」ではなく、「スケールの考え方」を中心にまとめました。
後日、ここで挙げた基本スケールそれぞれについて整理していこうと思います。